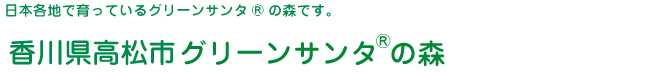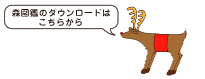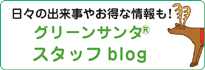香川県高松市のグリーンサンタの森は、高松市南部の西植田町に位置しています。周囲には讃岐平野の特徴である溜め池が点在し、緩い谷の中に集落と水田があるような里山の風景が広がっています。森はヒノキ植林と竹林で構成されており、植林の手入れや竹林の利用の仕方など、人と里山の自然の関わりなどを学習することができます。また、森の周囲には広葉樹林もあり、様々な植物やそれらと関わりのある動物についても学ぶことができます。
![]()
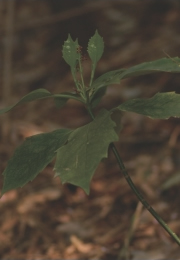
アオキ
「いつまでたっても、茎が青い木」という意味の名前を持つアオキ科の木です。比較的、暗い場所や湿った場所でも育つことができます。

カンサイタンポポ
関西から西に多く生息が確認されている日本在来のタンポポ」です。花の時に茎が長く、ガクが反り返らず、春にしか花を咲かせないのが特徴です。香川県グリーンサンタの森では森の縁の日当たりのよい場所に数多く咲きます。

アマドコロ
「甘く食用になるトコロ(イモ)」という意味の名前を持つユリ科の草です。名前の由来通り、茎や根が甘く食用になりますが、似た種類に毒をもつものがあるので、注意が必要です。

シダの仲間
香川県高松市のグリーンサンタの森では、イノデの仲間やソテツの仲間などのシダの仲間も数多く見ることができます。

イチヤクソウ
昔から「薬草」として利用されたことから、一薬草と呼ばれるイチヤクソウ科の草です。葉の斑が非常に美しい植物です。

ジャノヒゲ
別名「リュウノヒゲ」とも呼ばれるユリ科の草です。生い茂る細い葉が龍の髭を連想させます。また、冬の頃にコバルトブルーの奇麗な種子をつけます。
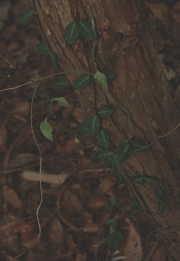
テイカカズラ
平安時代の藤原定家がツタになって皇女の墓石にまとわりついた」という昔話が名前の由来となっています。キョウチクトウ科の仲間のツタで、若い個体は非常に斑の奇麗な葉をしています。

ヒノキ
一説に「油を含み、火がつきやすい木」という語源を持つヒノキ科の木です。日本では最高品質の建材として扱われています。

ドクダミ
「毒をため込む」「体の毒を出す」など、様々な説の名前の由来を持つドクダミ科の草です。草をもむと独特な臭いがあり、「十薬」という名前で生薬やお茶としても利用されます。

ヒメウズ
「小さなウズ(トリカブト)」という意味の名前を持つキンポウゲ科の草です。林縁やあぜ道に小さく清楚な花をつけます。

ナガバノタチツボスミレ
タチツボスミレに似て、葉が長くなるスミレ科の植物です。スミレの語源は、「花の形が大工道具の墨つぼ」に見えることからと言われ、とても特徴的な形をした花です。

マダケ
とてもまっすぐに延びるイネ科の竹です。竹の肉が厚すぎず・薄すぎず・折り曲げなどにも強く・竹細工などの材料に適しているとされ、昔から活用されてきました。

ヒイラギ
葉のトゲトゲが美しい、モクセイ科の木です。語源は「葉のトゲに触れると疼(ひいら)ぐ木」と言われます。常緑で害虫にも強いことから、昔から魔よけとして使われてきたそうです。

ヤブジラミ
いわゆる「ひっつきむし」の仲間で、「くっつくその姿をシラミに見立てた草」という意味の名前を持つセリ科の草です。小さく可憐な花なのに可哀想な名前の由来です。

ヤブツバキ
「艶のある葉をもつ木」という意味の名前を持つツバキ科の木です。赤い美しい花を咲かせ、メジロなどの野鳥が蜜を吸いにやってきます。

ヤブラン
「藪の中で、ラン科の植物の似た葉の草」という意味の名前のユリ科の植物です。ラン科では無いところがややこしいですが、冬に真っ黒でキレイな種子をつけます。
![]()

アカネズミの巣穴
山地に広く生息しているノネズミの仲間の巣穴が、木の根元や地面にたくさんありました。おそらくアカネズミ、あるいはヒメネズミのものでしょう。クルミやドングリなどを蓄えたり、巣を作るために木の葉を運び込んだりしているはずです。この巣穴から、周辺の林に食べ物を探しに出かけているのでしょうね。

イタチの仲間のフン
ニホンイタチかチョウセンイタチか、あるいはテンのコドモのフンかもしれません。彼らのフンは、川や用水路など、今回のように水路の近くでよく見かけます。山の中では、倒木や石の上など目立つところでもよく目にします。なわばりの主張や異性へ向けてのアピールなど同種間でのコミュニケーションに役立っていると言われています。

タヌキ(?)のフン
尾根で、中型哺乳類のフンを見つけました。タヌキ?アナグマ?ハクビシン?中身は果実の種とサワガニです。少なくとも2回、同じ場所でフンをしたようです。タヌキがため糞をし始めたところかもしれません。近くの人に話を聞くと、「タヌキとハクビシンは見たことがあるけど、アナグマは見たことがないし、見たという話も聞いたことないなぁ」とのことでした。

ニホンイノシシの掘り返し跡
ニホンイノシシは鼻の力が非常に強く、鼻で地面を掘り返して食べ物を探すのが得意です。まだ地面に顔を出していないタケノコやヤマノイモ、クズの根などの植物や、ミミズなど、地中にも大好物がたくさんあります。ここヒノキ林の中で見つけたものは、何だったのでしょうか。

ニホンイノシシの体擦り跡
シカやイノシシは時々、水たまりなどで泥浴びをします。その後、体を木の幹などにこすりつけることが多いので、泥がついた立ち木や竹が、林内のけもの道沿いに何箇所もありました。体を木の幹にこすりつけるのは、体についた寄生虫を取ったり、かゆいところをかいたりするためです。

猛禽類の食事跡
林内にスズメの羽毛が散乱していました。羽軸がきれいに抜かれているので、猛禽類が食事をした跡だろうと推測することができます。この大きさの小鳥をねらうのは、ハイタカかツミあたりでしょうか。